糖尿病は、人間だけでなく犬も発症する病気です。犬の糖尿病に対処するためには、早期発見することが非常に重要ですが、症状がわかりにくく、進行すると重篤な合併症を引き起こす危険もあります。
この記事では、犬の糖尿病の症状や原因、診断方法から、治療法、そして予防法まで、獣医師が徹底的に解説します。大切な愛犬と長く健康に暮らすために、一緒に糖尿病について学びましょう。
犬の糖尿病とは?病気のメカニズムを解説
犬の糖尿病は、人間と同様にインスリンと呼ばれるホルモンの作用不足によって血糖値が高くなる状態が続く病気です。インスリンとは、膵臓から分泌され、血糖を細胞内に取り込み、エネルギーとして利用したり貯蔵したりする役割を担うホルモンです。
糖尿病になると、細胞がブドウ糖を利用できなくなり、代わりに脂肪やタンパク質を分解してエネルギーを得ようとします。この過程でケトン体が増え、「糖尿病性ケトアシドーシス」という重篤な状態に陥ることもあります。
さらに、高血糖状態が続くと、白内障や神経障害など様々な合併症を引き起こすこともあるため、糖尿病は非常に危険な病気です。
犬の糖尿病の種類

犬の糖尿病には、大きく分けて以下の2種類があります。
- インスリン依存性糖尿病(1型糖尿病)
- インスリン非依存性糖尿病(2型糖尿病)
インスリン依存性糖尿病(1型糖尿病)
犬の糖尿病のほとんどは、このインスリン依存性糖尿病です。膵臓のインスリンを分泌する細胞(β細胞)が破壊され、インスリンがほとんど、または全く作られなくなることで発症します。
自己免疫疾患や膵炎などが原因となることがあり、多くの場合、生涯にわたるインスリン注射が必要となります。遺伝的な素因を持つ犬種(プードル、ミニチュアシュナウザーなど)が発症するケースが多いです。
インスリン非依存性糖尿病(2型糖尿病)
人間の糖尿病ではよく見られますが、犬では稀なタイプです。膵臓からのインスリン分泌はありますが、体の細胞がインスリンに対して適切に反応しない「インスリン抵抗性」が生じることで血糖値が上昇します。
肥満が主な原因となることが多く、食事療法や運動療法、内服薬で改善が見られることもありますが、進行するとインスリン療法が必要になる場合もあります。
犬が糖尿病になった際の症状

犬が糖尿病になると、体内でブドウ糖が適切に利用されなくなり、さまざまな症状が現れます。これらの症状は初期には気付きにくいこともありますが、進行すると重篤な状態になるため、早期発見が非常に重要です。
初期症状
糖尿病の初期段階では、主に以下の症状が発生します。
- 多飲多尿
- 体重減少
- 活動量低下
多飲多尿
多飲多尿は、糖尿病の最も典型的な初期症状です。血液中の糖分濃度が高くなると、体は余分な糖を尿として排出しようとします。
その際に大量の水分も一緒に排出されるため、おしっこの量が増え、結果として水をたくさん飲むようになります。
体重減少
細胞がエネルギーとしてブドウ糖を利用できないため、代わりに筋肉や脂肪を分解してエネルギーを得ようとします。そのため、食欲旺盛にもかかわらず体重が減少していくというメカニズムです。
活動量低下
エネルギーが不足するため、愛犬が以前よりも元気がなくなり、遊ぶ量や散歩の時間が減るといった変化が見られることがあります。早期発見するためには、日頃から愛犬の様子や活動量を気にかけておくことが重要です。
進行した症状・合併症
糖尿病が進行し、血糖コントロールが不良な状態が続くと、以下のようなさまざまな合併症を引き起こし、命に関わることもあります。
- 白内障
- 糖尿病性ケトアシドーシス
- 神経障害
- 感染症
白内障
犬の糖尿病でよく見られる合併症です。高血糖により目の水晶体が濁り、視力が低下したり、最終的に失明に至ることもあります。
糖尿病性白内障は進行が非常に早く、数週間で急激に悪化することもあるため、早期発見と早急な治療が重要です。
糖尿病性ケトアシドーシス
非常に重篤な合併症で、緊急治療が必要です。インスリンが極度に不足し、脂肪の分解が進みすぎてケトン体という酸性の物質が血液中に大量に蓄積される状態です。
糖尿病性ケトアシドーシスになると、嘔吐、食欲不振、下痢、元気がなくぐったりする、呼吸が荒い、意識障害、特徴的な甘酸っぱい口臭(アセトン臭)などの症状が現れます。この状態に陥ると命に関わるため、すぐに動物病院を受診しましょう。
神経障害
高血糖が続くことで、神経にダメージが生じ、後ろ足がふらつく、歩き方がおかしくなるなどの症状が見られることがあります。
感染症
高血糖は免疫力を低下させ、細菌や真菌が繁殖しやすい環境を作ります。そのため、皮膚炎、膀胱炎(頻尿、血尿など)、肺炎などの感染症を繰り返しやすくなります。
犬が糖尿病になる原因

犬の糖尿病は、複数の要因が絡み合って発症すると考えられています。主な原因は以下の通りです。
- 膵臓の機能不全
- 遺伝的要因
- 薬剤の副作用
- ホルモン疾患
膵臓の機能不全
犬の糖尿病は、膵臓にあるインスリンを分泌する細胞(β細胞)が破壊され、膵臓の機能不全になることで発症するケースが多いです。自己免疫によってインスリンを分泌するβ細胞を攻撃したり、膵臓が炎症を起こす膵炎になったりすることで、インスリンの分泌が減少して、糖尿病を引き起こします。
遺伝的要因
特定の犬種は、遺伝的に糖尿病を発症しやすい傾向があります。
- プードル
- ミニチュアシュナウザー
- ダックスフンド
- サモエド
- ビーグル
- ケアンテリア
- シェットランドシープドッグ
これらの犬種は、他の犬種に比べて膵臓のβ細胞の脆弱性やインスリン感受性の違いなど、糖尿病になりやすい遺伝的素因を持っていると考えられています。
薬剤の副作用
特定の薬剤、特にステロイド剤の長期使用は、血糖値を上昇させ、インスリン抵抗性を引き起こすことで糖尿病を誘発する可能性があるため、注意が必要です。これは「医原性糖尿病」と呼ばれます。
他の病気の治療のためにステロイドを使用している犬は、定期的な血糖値のチェックが必要です。
ホルモン疾患
体内のホルモンバランスの乱れが糖尿病を引き起こすことがあります。代表的なのは「クッシング症候群(副腎皮質機能亢進症)」です。
これは、副腎からコルチゾールというホルモンが過剰に分泌される病気で、コルチゾールには血糖値を上げる作用やインスリン抵抗性を引き起こす作用があります。これによって、糖尿病を誘発したり悪化させたりします。
また、不妊手術をしていないメス犬の発情期に分泌される女性ホルモンも、インスリン抵抗性を引き起こし、糖尿病のリスクを高めることがあるということを理解しておきましょう。
犬の糖尿病の診断方法
犬の糖尿病の診断においては、血液検査と尿検査の両方を行うことが一般的であり、非常に重要です。
血液検査では、血液中の血糖値を測定して高血糖であるかどうかを判断します。また、「フルクトサミン」や「グリコヘモグロビン」といった項目も測定することで、平均血糖値を確認し、一時的な血糖変動に左右されない正確な診断が可能です。
血液検査だけでなく、尿検査も糖尿病の診断には欠かせません。健康な犬の尿には、通常、糖はほとんど含まれませんが、糖尿病の場合はブドウ糖が尿中に漏れ出し、「尿糖」として検出されます。さらに、糖尿病が重症化してケトアシドーシスの状態になると、尿中にケトン体が検出されることもあります。
自宅で血糖値を測定する検査キットも存在しますが、糖尿病の疑わしい症状が見られる場合には必ず動物病院で受診し、獣医師による適切な診断と指導を受けるようにしてください。
茶屋ヶ坂動物病院|健康診断のご案内犬の糖尿病の治療法

犬の糖尿病の治療は、主にインスリン療法が中心となり、それに加えて食事療法と運動療法を組み合わせるのが一般的です。合併症を引き起こしたり、他の病気によって引き起こされたりしている場合は、その症状に合わせた治療も必要になります。
インスリン療法
犬の糖尿病は、膵臓からのインスリン分泌がほとんどない1型糖尿病が多いため、不足しているインスリンを外部から補給するインスリン注射が治療の基本です。獣医師が犬の体重や血糖値の推移に合わせて適切な種類のインスリンと投与量を決定し、飼い主が自宅で皮下注射を行います。
毎日決まった時間に、決まった量のインスリンを投与することが、血糖値を安定させるために非常に重要です。
食事療法
糖尿病の犬には、血糖値の急激な上昇を抑えるための専用の「療法食」を与えることも治療法の1つです。療法食には、一般的に食物繊維が豊富に含まれており、食後の血糖値の上昇を緩やかにするよう工夫されています。
食事の量や回数も、インスリンの作用時間に合わせて厳密に管理することが大切です。肥満の犬の場合は、同時に体重管理も行い、理想体重を目指すことでインスリンの効きを良くする効果も期待できます。
運動療法
適度な運動は、血糖値のコントロールに役立ちます。運動によって筋肉がブドウ糖を消費するため、血糖値を下げる効果があります。
しかし、過度な運動は急激な低血糖を引き起こす可能性があるため注意が必要です。獣医師と相談し、愛犬の体力や状態に合わせた無理のない範囲で、毎日規則正しい運動を続けることが重要です。
運動量や時間も、インスリン投与量や食事量とのバランスを考慮して一定に保ちましょう。
その他の治療
糖尿病が他の病気(膵炎、子宮蓄膿症など)によって引き起こされている場合は、その基礎疾患の治療も並行して行われます。また、白内障などの合併症が進行している場合は、それぞれの症状に応じた対症療法や外科的治療が必要になることもあります。
これらの治療を継続的に行いながら、定期的な血液検査や尿検査で血糖コントロールの状態をモニタリングし、必要に応じて治療計画を調整していくことが重要です。
犬の糖尿病リスクを低下させる予防法

愛犬が糖尿病になるリスクを少しでも低下させるためには、以下の予防法を日頃から意識しましょう。
- 適切な食事・体重管理
- 定期的な運動
- 日頃の体調管理
適切な食事・体重管理
糖尿病を予防する方法として最も重要なのは、バランスの取れた食事を与えることと適切に体重を管理することです。肥満はインスリン抵抗性を高め、糖尿病のリスクを大幅に上昇させるため、犬の年齢や活動量に応じた適正な量の食事を与え、おやつの与えすぎには注意しましょう。
定期的な運動
定期的な運動は、肥満予防だけでなく、筋肉がブドウ糖を効率的に利用するのを助け、インスリンの働きを改善する効果も期待できます。毎日無理のない範囲で散歩や遊びの時間を設け、愛犬の健康維持に努めましょう。
日頃の体調管理
日頃から愛犬の飲水量、排尿量、食欲、体重の変化に注意を払うことも大切です。これらの変化は糖尿病の初期症状である可能性があり、早期に異変に気付くことで、早期の診断と治療に繋がり、病気の進行や合併症のリスクを抑えることができます。
年に一度の定期的な健康診断も、潜在的な問題を早期に発見するために非常に有効です。
愛犬が糖尿病になってしまったら
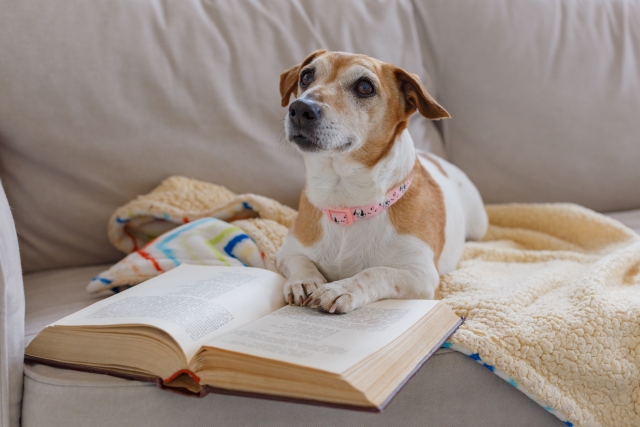
愛犬が糖尿病になってしまったら、不安や戸惑いを抱えてしまうでしょう。しかし、そんな時こそ冷静で適切なケアを行うことを心がけましょう。
糖尿病は、飼い主の日々のケアと獣医師との連携によって、十分に管理できる病気です。大切なのは、愛犬の糖尿病を「特別なこと」と捉えすぎず、生活の一部として受け入れる心構えです。
インスリン注射や食事管理は、最初は難しく感じるかもしれませんが、必ず慣れます。焦らず、愛犬のペースに合わせて取り組んでいきましょう。規則正しい生活リズムを保ち、ストレスを減らすことも血糖コントロールには重要です。
困ったことや不安なことがあれば、すぐにかかりつけの動物病院で獣医師にご相談ください。適切な治療と日頃のケアで糖尿病を克服して、愛犬が幸せな生活を送れるようにサポートしましょう。
糖尿病の疑いがある場合はすぐに動物病院へ
犬の糖尿病について、そのメカニズムから症状、原因、診断方法、そして治療法や予防法まで詳しく解説しました。
犬の糖尿病は、多飲多尿や体重減少といった初期症状に気づき、早期に適切な治療を開始することが、合併症を防ぎ、愛犬が快適に過ごすために非常に重要です。インスリン療法を中心に、食事や運動管理が愛犬の生活の質を大きく左右します。
もし愛犬に糖尿病の疑わしい症状が見られる場合は、迷わずすぐに動物病院を受診し、獣医師の診断と指導を受けてください。愛犬と長く健康に暮らすために、一緒に病気と向き合いましょう。










